「人道的配慮」で永続する年間1200億円の税金投入。
およそ7万人の外国人が受ける生活保護。
在留資格の偽装、収入隠し、母国資産の未申告——次々と暴かれる巧妙な手口。
表面化する不正受給の実例を追跡しながらも、「人道的配慮」を理由に制度が「廃止できない」複雑な背景に迫る。
少子化日本が労働力として、外国人に依存せざるを得ない現実。
年々膨らむ支出に「私たちの税金がなぜ?」と渦巻く不満。
この記事では、在日外国人の生活保護問題を徹底解説します。
外国人の生活保護受給者数、支給額はいくら?受給条件とは
ここ最近よく目にするようになった外国人への生活保護問題。
誰が、どのくらい受け取り、どんな条件が必要なのか。
税金の使い道として賛否両論を呼ぶこの問題の全貌に迫る。
外国人が生活保護を受けるための条件とは?

厚生労働省の通知によると、生活保護に準じた支援を受けられる外国人は限られた在留資格を持つ人だけだ。
対象となるのは、
- 永住者
日本に長期間滞在し、素行が良く、独立して生活できる資産や技能を持つ人。(在留期間は無期限) - 定住者
特別な理由により、日本での居住が認められた人。(日系3世や中国残留邦人などが該当) - 永住者の配偶者等
永住者や特別永住者の配偶者、または日本で生まれたその子ども。 - 日本人の配偶者等
日本人の配偶者、子ども、または特別養子。 - 特別永住者
第二次世界大戦前後に日本に居住し続けた在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫。(入管特例法による資格) - 認定難民
入管法で難民として認められた人。
実習生や留学生は対象にならない。
また、収入や資産が最低生活費より少ないこと、貯金がないこと、親族からの援助が得られないこと、他の社会保障制度が使えないことなど、生活に困っている状況であることも条件となる。
【驚きの実態】外国人生活保護受給者の人数と割合
厚生労働省の統計では、2024年末時点の外国籍生活保護受給者は約6万9千人、世帯数では約4万5千世帯となっている。
これは全体の生活保護受給者(約212万人)の約3.28%だ。
国籍別で見ると、韓国・朝鮮籍(在日同胞)が最も多く、次いで中国、フィリピン、ブラジル・ペルーの順だ。
在日同胞とは、日本の植民地支配によって日本に渡り、敗戦後も日本で生活するようになった朝鮮人とその子孫たち
【年間総額○○○○億円】外国人への生活保護支給額はいくら?
厚生労働省によると、日本全体の生活保護費は年間約3.8兆円で、そのうち外国人への支給額は約1200億円と見積もられている。
これは全体予算の約3%に当たる。
外国人の単身世帯では月に約8~12万円が支給され、家族が多い世帯ではそれ以上となり、この金額には日々の生活費、家賃、医療費などが含まれる。
外国人生活保護の問題点と廃止論争

外国人への生活保護をめぐり、続けるべきか止めるべきかの議論が熱を帯びている。
不正に受け取る例や国の財政負担が増えることを理由に、「やめるべきだ」との声が強まる一方、働き手として外国人に頼る日本の現実も見逃せない。
「やさしさ」と「公平さ」の間で揺れる制度の行方に、国民の関心が集まっている。
なぜ生活保護廃止は実現しないのか?理由は〇〇化
日本の生活保護法は本来「国民」を対象としているが、1954年の厚生省通知により、「人道的配慮」の観点から外国人にも広げられている。
これは国際協力や、基本的人権を守る考えに基づいた措置だ。
最高裁は2014年に「外国人は生活保護法の対象ではない」と判断したが、それでも行政の取り組みとして一定の条件を満たす外国人に支給が続いている。
外国人労働者は日本経済に欠かせない存在となっており、彼らの最低限の生活を保障することは社会全体の安定につながるとされる。
【外国人生活保護】不正受給の実態とは?
外国人による生活保護制度の悪用や不正受給には、
- 在留資格を偽る
虚偽の情報で在留資格を取得する行為(在留資格を不正に取得し、長期滞在を狙う) - 家族を呼び寄せて世帯人数を増やす
実際には同居していない家族を日本に呼び寄せ、支給額を増やす行為(世帯人数を増やして不正に支給額を増やす) - 母国の資産を隠す
海外にある資産を申告せず、無資産と偽る行為(海外資産を隠して受給資格を得ようとする) - 偽装離婚で単身世帯を装う
実際には婚姻関係を続けているにもかかわらず、離婚したと偽り単身世帯として申請する行為(生活保護を受けやすくするために形だけの離婚を行う) - 実際と異なる住所を申告する
実際には別の場所に住んでいるにもかかわらず、支給条件が有利な地域に住所を偽る行為(支給条件が緩和される地域に住所を偽る)
などの例がある。
具体的には、2024年5月に神戸市で74歳の男性が働いて得た収入を隠して約208万円を不正に受け取った例や、2024年1月に千葉市でガーナ国籍の男性が在留資格を療養目的に変えて生活保護を申請した例などがある。
2022年12月には愛知県安城市で外国人の生活保護申請をめぐる問題も起きた。
厚生労働省の統計によると、2020年度の不正受給は全体の約1.96%と報告されている。
少子高齢化が引き起こす問題とは?

日本は急速に少子高齢化が進み、働き手が足りないため外国人労働者を受け入れることが欠かせなくなっている。
外国人労働者は日本の経済を支える大切な存在となりつつあるが、その社会保障をどう整えるかが問題だ。
外国人労働者が安心して働ける環境を作ることは、日本の経済が成長するためにも重要となる。
【今後の課題】不正受給防止と適切な支援策の必要性

外国人の生活保護制度には、不正に受け取ることを防ぎつつ、本当に助けが必要な人に適切な支援をするという二つの課題がある。
厚生労働省は審査を厳しくしたり定期的な調査を行ったりと、不正を防ぐ対策を取っているが、同時に支援が必要な外国人への適切な保護も大切だ。
今後は、日本人と外国人の間で公平さを保ちながら、不正を防ぎつつ適切な支援を行う制度改革が求められている。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
外国人の生活保護問題は賛成か反対かだけでは語れない難しい問題。
今、約6万9千人、全体の3.28%の外国人が生活保護を受けており、年間約1200億円が使われている。
永住者や特別永住者などの特定の資格が必要で、一部には不正に受け取る問題もあるが、人道的な思いやりや国際的な協力の考えから廃止されていない。
これからは子どもが減り高齢者が増える中で働き手不足も考えながら、不正を防ぎつつ公平さを保つ制度づくりが必要だ。
社会全体で話し合いを深め、外国人も日本人も共に暮らしやすい社会を目指すことが大切だ。

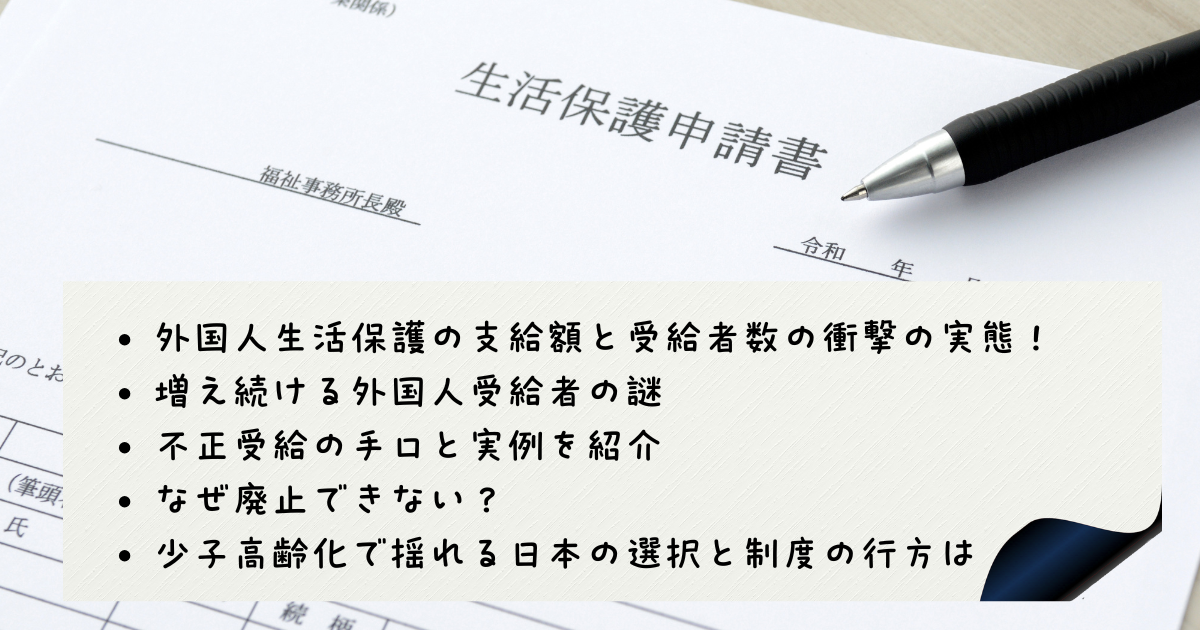
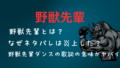

コメント