近年、日本で暮らす外国人の数が増え続けている。
2022年末には、在留外国人数が307万人を超え、初めて300万人台に達した。
この数字は前年比11.4%増という大幅な伸びを記録しており、こうした状況を背景に、社会の関心は自然と「外国人犯罪」へと向かうようになった。
しかし、実際のデータを紐解くと、その実態は一般的なイメージとは異なる側面も多く見られる。
外国人犯罪は、日本の総犯罪のわずか1.8%程度にとどまるものの、人口比で見るとやや高い傾向があるのも事実だ。
本記事では、最新の統計や具体的事例をもとに、外国人犯罪の現状と課題について掘り下げながら、多様性と安全を両立させるための展望を探っていく。
犯罪の統計から見る日本の治安~増加する外国人労働者~

外国人による犯罪は、日本の犯罪全体からすればごく一部にすぎない。
2022年の統計によると、外国人犯罪は約1万件で、日本の総犯罪件数56万8,104件の中ではわずか1.8%を占めるにとどまっている。
法務省の「令和3年版犯罪白書」からも、この傾向を確認することができる。
しかしながら、人口比で比較すると様相は少し変わってくる。
2019年のデータによれば、日本の総人口に対する犯罪発生率が10万人あたり約570件だったのに対し、外国人の犯罪率は10万人あたり約800件と、やや高い数値となっていた。
また、令和2年度末の検挙率を比較した場合、来日外国人とその他外国人がともに約0.3%であるのに対し、日本人は約0.2%と若干の差が認められる。
2023年上半期(1〜6月)の来日外国人による刑法犯・特別法犯の検挙件数は7,441件で、前年同時期と比べて389件増加していることから、外国人人口の増加に伴い、犯罪件数も緩やかな増加傾向にあることがうかがえる。
【外国人犯罪】国籍別の犯罪率・犯罪の内訳とは?

外国人による犯罪の内訳を分析すると、窃盗が全体の6割以上を占め、最多となっている。
これに続いて、傷害・暴行が11.3%、詐欺が6.6%、強盗が0.9%、殺人が0.5%という順になっている。
訪日外国人が関わる犯罪として特に目立つのは、詐欺やスキミング、偽造品の流通などだろう。
具体例を挙げると、2019年にはマレーシア人による偽造クレジットカード詐欺が急増し、2001年には中国人女性が、エステ店で客のクレジットカードデータをスキミングする事件が発生していた。
このほか、架空の外国人が被害者に国際送金を要求するロマンス詐欺や、ブラジル人グループによるひったくり・自動車盗、偽造クレジットカードを使って高級ブランド品を購入し本国へ持ち帰る組織的な犯罪なども報告されている。
こうした犯罪の特徴として、役割分担が明確な組織的犯行である点が挙げられる。
【国籍別の傾向】外国人犯罪率に見る国ごとの違いとその原因
令和2年度の国籍別刑法犯検挙状況を見てみると、ベトナムが2,931件(全体の31%)で最も多く、次いで中国が2,666件(28%)、ブラジルが682件(7%)、韓国が608件(6%)、フィリピンが339件(4%)と続いている。
ベトナムと中国の2か国だけで全体の約6割を占めており、この比率は在留外国人の人口比率とも概ね合致している。
治安リスクの深刻化?外国人受け入れ拡大による治安への影響

外国人の犯罪が発生する背景には、社会的・経済的要因など様々な理由が絡み合っている。
例えば、短期滞在者や不法滞在者による犯罪が多い理由として、安定した就労や生活基盤の欠如が指摘できる。
経済的苦境から、窃盗などの犯罪に手を染めるケースもあれば、言語の壁によって適切な情報にアクセスできないことから、犯罪に巻き込まれるパターンも存在する。
特に、不法滞在者は法的保護を受けにくく、経済的困窮から犯罪に走りやすい環境にある。
【外国人犯罪の背景と課題】治安悪化の要因を探る
外国人受け入れの拡大に伴い、いくつかの治安上の懸念が浮上している。
その一つが、来日外国人による犯罪組織の形成と活動の活発化だ。
過去を振り返ると、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、中国人による組織的な窃盗団が活動を拡大した事例がある。
これは、在留資格の緩和に伴う中国人来日者の増加と関連していると考えられている。
また、国際的な犯罪組織と日本の暴力団との連携強化も懸念材料だ。
2019年には外国人と日本の暴力団が手を組み、偽造クレジットカードを使用した詐欺事件が発生していた。
このような連携が強まる背景には、グローバル化による人的ネットワークの拡大や、犯罪手法の国際的な共有があると考えられる。
さらに看過できないのが、インターネットを介した新たな形態の詐欺の増加である。
SNSを利用したロマンス詐欺やフィッシング詐欺が台頭しており、匿名性の高さと国境を越えた被害拡散の容易さというインターネットの特性が、こうした犯罪の温床となっている。
言語の壁を越えて犯罪を行える点も、外国人犯罪者にとって魅力となっているようだ。
【 不法滞在者と犯罪の関係】日本の治安に与える悪影響とは?
不法就労や、不法滞在者による問題も軽視できない。
来日外国人の、刑法犯検挙人員に占める不法滞在者の比率は15.6%(8,892人中1,392人)だが、その内訳を詳しく見ると、凶悪犯(不法滞在者の比率38.0%)、知能犯(同40.9%)、侵入盗(同56.1%)といった重大犯罪では高い比率を示している。
不法滞在状態にあること自体が、より深刻な犯罪への関与リスクを高めている可能性は否定できないだろう。
海外事例に学ぶ!外国人労働者増加が日本の治安に与える影響と今後の展望

日本の状況を考える上で、海外の事例から得られる教訓は多い。
特に近年、移民政策の転換が鮮明になっている北欧諸国の例は参考になると思われる。
スウェーデンでは、2022年10月に就任したウルフ・クリステション首相が移民政策の「パラダイムシフト」を宣言。
第三国定住難民の受け入れ数を年間5000人から900人へと大幅削減し、労働移民の条件や家族呼び寄せの要件も厳格化した。
隣国デンマークも2024年1月1日から新たな規則を施行し、難民が母国に帰国した場合、滞在期間にかかわらず一時滞在許可を取り消す可能性を盛り込むなど、難民政策を厳格化している。
ただし、永住許可を持つ難民や、亡命以外の理由で渡航する難民には適用されないといった配慮もなされている。
これらの政策変化からは、難民の権利保護と国家安全保障のバランスをとることの難しさが浮き彫りになる。
日本もこうした海外の経験を参照しつつ、自国の実情に即した政策を模索していく必要があるだろう。
まとめ:多様性と安全の両立を目指して
日本社会が多様性を受け入れながらも、安全で秩序ある社会を維持していくためには、バランスのとれた政策と社会全体の理解が不可欠である。
外国人犯罪の問題は、単なる治安問題にとどまらず、社会統合や人権、経済など多岐にわたる課題と密接に関連している点を忘れてはならない。
外国人犯罪は全体から見れば少数であるものの、人口比では若干高い傾向が見られる。
その背景には言語や文化の壁、経済的困窮、不法滞在など複合的な要因が存在することから、多文化共生社会の実現、経済的支援、法執行の強化、啓発活動、入国管理の適正化など、多面的なアプローチが必要となってくる。
今後、日本がより開かれた社会を目指す中で、外国人との共生は避けて通れない道となるだろう。
犯罪対策を講じながらも、外国人の人権を尊重し、彼らの能力を活かせる社会づくりを進めることが、日本の発展と安全の両立には必要不可欠だろう。
この複雑な問題に対しては、政府、地方自治体、市民社会、そして外国人コミュニティ自身が協力し、継続的な対話と政策の改善を重ねていくことが求められる。
そうした取り組みを通じてこそ、多様性と安全が調和する、真の意味での国際化した日本社会の実現が可能になるのではないだろうか。

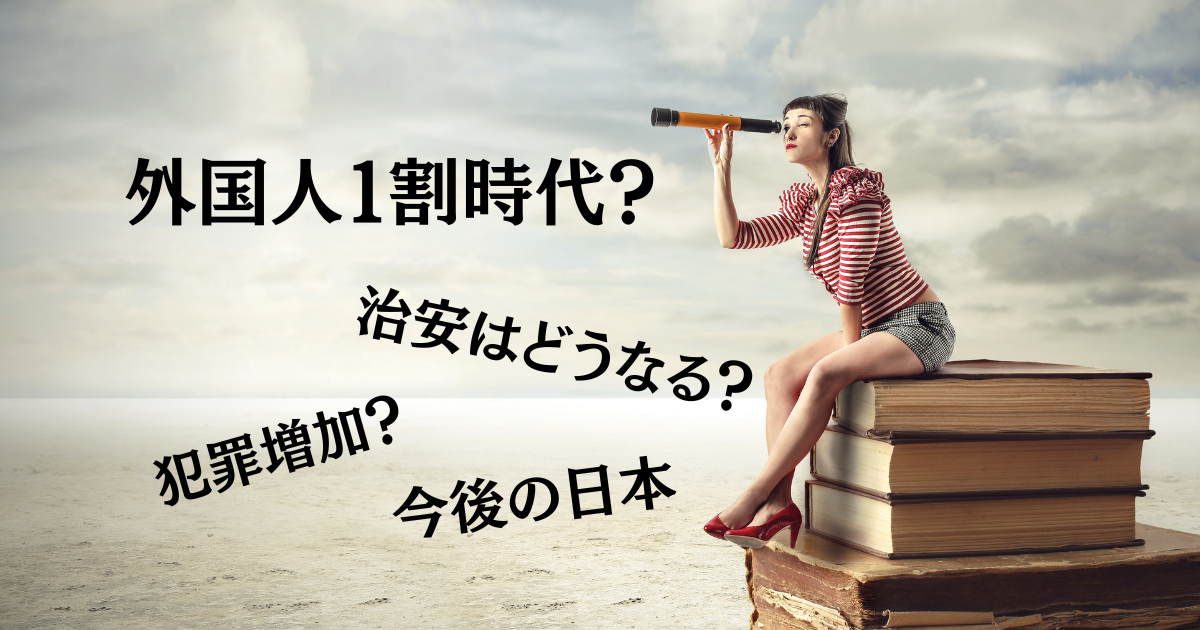
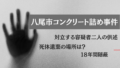

コメント