教室を走り回る男子児童の頭を平手で叩いた北海道の小学校教師が減給処分に。
厳格化する体罰規制の中、教育現場には戸惑いの声が広がっている。
『子どもの安全を守るための対応が体罰と判断される』
『このままでは教師は何も指導できなくなる』
という現場の葛藤と、法律が定める体罰の基準とは―。
増える不適切指導の処分件数と減少傾向の体罰。
教育指導の在り方が問われている。
【体罰問題】小学校教師(61)が頭を平手で叩いたとして懲役処分
今回の事件は、2024年5月北海道の小学校で発生した。
授業中に教室を飛び出した低学年の男子児童2人を教師が教室に連れ戻したが、その後も児童が教室内を走り回ったため、感情的になった教師が右の平手でそれぞれの児童の頭を1回叩いた。
児童にけがはなかったものの、男性教師は「いいかげんにしなさい」と叱ったが、児童が言うことを聞かなかったために叩いたとされる。
この件は別の児童の保護者から話があり、学校側が把握した。
男性教師は「けがにつながる危険な行為を止めたかった。感情のコントロールができなかった」と説明している。
【教育現場の現実】懲役処分の内容とその理由
北海道教育委員会は、この61歳の男性教師に対して3月11日付けで減給1か月の懲戒処分を行った。
この処分は、学校教育法で明確に禁止されている体罰に該当すると判断されたためだ。
【 体罰とは?】法律で定義される判断基準
学校教育法第11条では体罰が明確に禁止されている。
文部科学省の通知によると、体罰の判断基準は以下の2点だ。
- 児童生徒の身体に対する侵害を内容とするもの
- 児童生徒に肉体的苦痛を与えるもの
体罰の判断は個々の事案ごとに、以下の要素を総合的に考慮して行われる。
- 対象となった児童生徒の状況(年齢、健康状態、心身の発達状況)
- 当該行為が行われた状況(場所、時間)
- 行為の態様(頻度、程度、意図)
ただし、緊急時の安全確保のための必要最小限の有形力の行使は、状況によっては体罰に該当しない場合もある。
【過去の体罰事例】発生率や処分の推移
2020年度のデータでは、体罰による処分を受けた教職員数は147人で前年度の223人から減少している。発生率は0.99%(本務教員数に対する割合)だった。
2020年度の学校種別の傾向では、中学校で123件、高等学校で19件の体罰が報告された。
体罰で懲戒処分を受けた教員104人のうち、減給または戒告が91人、免職が1人、停職が12人だった。
一方で、2013年の調査では公立学校での体罰発生件数が5,415件、体罰があった学校が全体の10.08%(3,603校)に上り、体罰による処分を受けた教職員数が2,752名と前年度の約7倍に急増していた。
これは体罰の定義や報告基準の厳格化によるものと考えられる。
【生徒指導の難しさ】言うことを聞かない生徒への対応
効果的な生徒指導には対話を重視し、生徒が冷静になるまで待ち、教員も冷静に話を聞くこと、一方的な非難を避けることが重要だとされる。
ベネッセの調査によると、保護者が担任教師に求めることとして以下が挙げられている。
- 一人ひとりを尊重すること
- コミュニケーションがとりやすいこと
- 授業が充実していること
これらの期待は必ずしも厳しい叱責や罰を求めるものではなく、むしろ個々の生徒に寄り添う姿勢を重視している。
また、岐阜大学の研究によると、中学生は「厳しさ」因子よりも「信頼」と「親しみ」の因子が相対的に高く、厳しい指導では意欲的に学習できないと感じていることが明らかになっている。
生徒指導の定義
2022年12月に改訂された生徒指導提要によると、生徒指導の定義は
「児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のこと」
とされている。
この定義は単に注意や罰を与えるだけでなく、児童生徒の自発的・主体的な成長を支援することを重視。
言うことを聞かない児童生徒への対応としては、一方的な叱責よりも対話を通じた指導が効果的だとされる。
しかし現場の教師からは
「言うことを聞かない子供に対してしっかり注意できない」
「教師の行動が委縮してしまう」
という懸念の声も多く上がっているのが現状だ。
【 海外の教育現場に学ぶ】アメリカの体罰とその対応
アメリカでは問題行動を示す生徒への対応は明確なマニュアルに基づいて行われる。
一般的な手順としては、まず教員が生徒に対し口頭で注意を与え、行動改善を促す。
生徒が改善しない場合は校長や副校長に報告され、さらに状況が改善しない場合は警備員や警察が呼ばれることもある。
また、アメリカでは州ごとの法制度に基づき教員の権利が保障されており、教員組合が州政府や学区と交渉し、労働条件や待遇を改善する制度がある。
教員が問題行動への対応中に訴訟リスクを負わないよう、州法で保護されている点も特徴だ。
【教育現場の変化】処分基準の厳格化とその影響
体罰による処分は減少傾向にあるが、不適切指導による処分は増加している。
2023年度のデータでは、体罰による処分は前年度比54人減の343人となった一方で、不適切指導による処分は91人増の509人で過去最多となった。
これらのデータから、体罰事案はやや減少している一方で、不適切指導による処分が増加していることがわかる。
【教師が怒れない時代】 教育現場の現実と課題
体罰禁止が厳格化される一方で、問題行動への対応マニュアルや外部機関の介入システムは日本では十分整備されていない。
このため、教員が直接的な対応を迫られるケースが多く、負担増加や委縮につながる懸念がある。
処分の厳格化について、
「こういうニュースが出て教師の立場が弱くなると将来教師を目指す人は大幅に減る」
「教員が強く指導できないことで教育の質が下がる」
「何でも体罰と一括りにするのはどうかと」
という意見もあり、教師の権限と責任のバランスをどう取るかが課題となっている。
まとめ
小学生を叩いた教師の体罰事件は、現代の教育現場が抱える複雑な問題を映し出している。
体罰は法律で禁止されているが、問題行動を示す児童生徒への効果的な対応策については現場の教師が模索している状況だ。
アメリカのように明確なマニュアル作成や外部機関との連携、社会的支援強化など、教員の保護と教育の質向上のための取り組みが日本でも求められている。
子どもの成長を支える教育と、教師の指導権限の適正なバランスを模索することが今後の課題だろう。

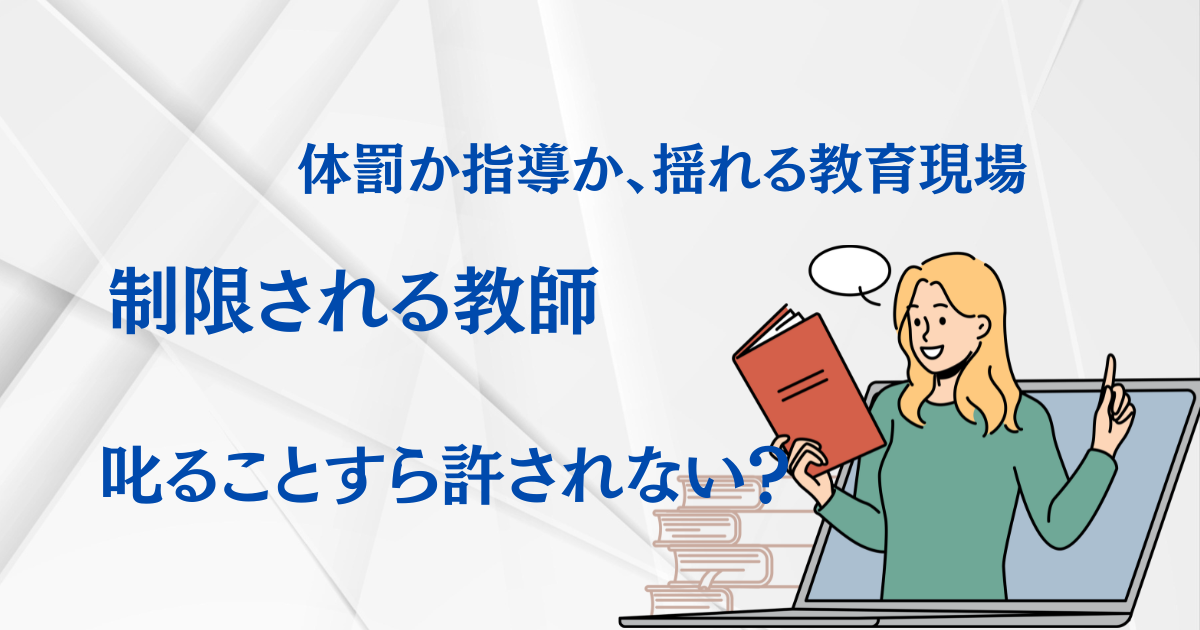
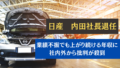

コメント