日本の大学に中国人留学生が急増し、その数は11万人を突破。
学費全額免除や返済不要の奨学金など、手厚い優遇措置に多くの日本人から疑問の声が上がっている。
なぜこれほど多くの中国人学生が日本を目指すのか?
円安による留学コストの低下、日本独自の優遇制度の魅力、そして少子化に悩む日本の大学側の事情が複雑に絡み合っている。
一方、留学生急増は医療費高騰や就職市場での競争激化など新たな社会課題を生み出している。
国民健康保険を利用した高額医療の受診後に帰国するケースや、限られた就職枠をめぐる日本人学生との競争激化など、その影響は多方面に広がっている。
政府が掲げる2033年「留学生40万人計画」は日本の国際化と少子高齢化対策の切り札となるのか、それとも社会的軋轢を深める要因となるのか。
教育の質保証と社会統合のバランスを模索する日本の課題と展望を徹底解説する。
【11万人超】 日本の大学に進学する中国人留学生が急増

日本の大学や専門学校で学ぶ中国人留学生が増加。
2025年現在、日本に来る中国人留学生は、11万人台後半から12万人台前半程度と推測される。
中国人留学生が増加した背景には、日本特有の学費免除や奨学金制度、そして中国国内の競争激化がある。
【留学生への優遇措置】学費免除や奨学金が与える影響とは
日本では、外国人留学生に対してさまざまな支援制度が用意されている。
代表的な「国費外国人留学生制度」では、月額11万7,000円から14万5,000円の生活費が支給され、学費は全額免除される。
さらに、往復航空券も提供されるという手厚い内容だ。
申請には在外日本大使館か日本の大学を通じた手続きが必要で、個人での直接申請はできない。
応募資格は、「日本に関心があり「12年間の学校教育を修了」「日本語学習に意欲的な者」となっている。
また、日本学生支援機構(JASSO)による奨学金も提供されており、私費留学生には月額48,000円が支給される。
【10年で〇倍!?】東大や早稲田大学は「中国人だらけ」?
東京大学では、全在籍者の12%以上が中国人留学生だ。
2024年時点でその数は3,396人に達し、ここ10年で約3倍に増加した。
同様に早稲田大学も、中国では福原愛(卓球)の出身校として屈指の知名度を誇り、約3,300人の中国人留学生が在籍している。
【なぜ日本に来るのか?】 中国人留学生が日本を選ぶ理由を解説
中国人留学生が日本を選ぶ理由にはいくつかの要因がある。
まず、中国国内で過熱する受験戦争からの逃避だ。
中国では毎年1,300万人以上が大学入試を受験する一方で、日本は比較的進学しやすい環境と認識されている。
地理的・文化的な近さも重要なポイントで、中国から3~4時間程度で到着でき、漢字文化圏であるため言語の壁が比較的低い。
経済面では、欧米と比べて学費が安く、円安の影響で生活費も割安になっている。
また、中国の大学入試「高考」で日本語が選択可能になり、日本語学習者が増加していることも一因だ。
就職機会の面でも、中国国内の厳しい就職事情に比べ、日本では就職や進学の機会が豊富だと考えられている。
【不平等?】 外国人留学生への返済不要な給付型奨学金の実態
一方で、留学生の急増は日本社会に新たな課題をもたらしている。
外国人留学生への優遇措置が手厚く、その公平性について国内では議論が続いている。
日本人学生の場合、多くが返済義務のある貸与型奨学金を利用し、返済には金利がつくことも。
一方で、外国人留学生の給付型奨学金は返済不要であり、渡航費まで支援される。
これにより、「日本人学生が苦しい状況にある中で、外国人留学生ばかりが優遇されている」という批判が高まっている。
今後、日本政府と教育機関は、支援制度と受け入れ体制を見直し、多様性を尊重しながら社会との調和を図る政策を進める必要があるだろう。
【日本の大学】なぜ留学生の受け入れ体制を強化するのか?

日本の大学や政府が中国人留学生を積極的に受け入れる背景には、複数の目的がある。
少子化対策から国際競争力の強化まで、その理由は多岐にわたっている。
現在、日本の大学(特に私立大学)は少子化による学生数減少に直面。
中国人留学生の受け入れは、「定員割れ防止」と「大学運営の安定化」に直接寄与している。
2025年1月時点での外国人留学生数は36万8,589人に達し、過去最高を記録。
そのうち中国人留学生は11万人台後半から12万人台前半程度と推測される。
東京大学では全学生の12%以上、早稲田大学では約3,300人が中国人留学生となった。
この数字は多くの大学にとって、経営を支える重要な柱となっている。
日本政府「留学生受け入れは国際交流政策の一環」
政府は「留学生受け入れは国際交流政策の一環でもあり、相互理解を深める狙いがある」と説明。
若い世代の交流を通じた相互理解は、将来の日本にとって重要だと位置づけている。
また、高い学力や専門性を持つ留学生を日本社会で活躍する高度人材として育成する目的も存在する。
特に理系分野では、研究開発力の強化につながる優秀な人材の確保が目的となっているようだ。
日本政府「2033年までに留学生〇〇万人を目指す」
日本政府は、2033年までに留学生40万人受け入れを目標に掲げた。
この目標達成に向け、具体的な取り組みとして、留学生が安心して学べる教育環境の整備や日本語教育の充実、インターンシップ拡充や在留資格の見直しなどの就職支援を進めている。
また、地方創生の観点から、都市部だけでなく地方大学への留学生誘致による地域活性化も重要な政策目標となっている。
これらの取り組みは、日本の国際競争力を高め、労働力不足への対応も視野に入れた総合的な国家戦略の一環と言える。
在日中国人家庭の中学受験熱!中国特有の「攀比」文化とは?

在日中国人家庭の間で、小学校低学年からの塾通いと、中学受験熱が高まっている。
この背景には、コロナ禍での教育環境の違いや、中国特有の競争文化が影響している。
【コロナ後】在日中国人家庭の中学受験と塾通いの増加傾向
コロナ禍で学校が休校となった際、中国国内では迅速にオンライン授業が導入された。
一方、デジタル化が進んでいなかった日本の学校現場は長期間混乱。
この差を目の当たりにした在日中国人の親たちは「日本の教育環境では子どもが遅れる」と危機感を抱き、塾通いや中学受験に力を入れるようになった。
日本の旧帝大や、早稲田大学などはブランドイメージがあり、教育力のあることで中国でも広く知られている。
そのため在日中国人家庭はこれらの大学を将来の進学先として視野に入れ、その準備段階として名門中学への入学を目指すケースが増えている。
「攀比(パンビー)」
中国語で「攀比(パンビー)」とは競争意識を表す言葉で、他者と比較し優越感を得ようとする行動で、俗に言うマウントを意。
在日中国人家庭ではこの文化が中学受験や塾選びにも影響し、「隣の家の子どもより良い塾へ」という意識が広まった。
【 教育現場での影響】中国人留学生と在日中国人の増加がもたらす課題とは?

最近の教育現場では、言語や文化の違いに対応するため、カリキュラムや指導方法の見直しも課題になっている。
また、特定地域や学校で、中国人留学生や在日中国人家庭が集中していることも課題に。
都市部では中国人留学生や移住者の増加により、家賃や不動産価格が上昇。
一部地域では地元住民との軋轢も報告されているなど、複数の課題が表面化してきた。
この状況に対し、「学校の収入を増やすためだけに留学生を受け入れるのではなく、少子化に合わせて学校数を減らすべき」という意見も出ている。
【中国人留学生×医療費高騰問題】 高額医療受診後、中国へ帰る?

中国人留学生の増加により、医療費の高騰が問題となっている。
中国での医療費は日本の2.5倍以上とされ、留学生が帰国して受診するケースも増加。
これにより、保険会社の支払い負担が増大している。
「帰国して受診」とは、留学生が日本に滞在中に公的医療保険(国民健康保険:国保)に加入し、その保険を利用して高額な医療を受けた後、自国に戻るケースを指す。
具体的には、留学や経営目的で日本に3か月以上滞在すると、国保への加入が義務付けられる。
保険料は前年度の収入に基づくため、留学生の場合は最低額(月数千円)で済む。
日本では自己負担が1~3割で済み、高額療養費制度を利用すればさらに負担が軽減される。
この制度を活用し、高額な医療を受け、治療後に自国へ帰ることで、日本の医療費負担だけが増加する結果となっている。
外国人労働者増加で医療費負担増!外国人患者の医療費未払い問題
少し話は変わるが、外国人労働者の増加も、社会保障制度に影響を与えている。
具体的な課題として、外国人労働者が海外に住む家族を「扶養家族」として日本の医療保険に登録するケースがある。
この場合、海外居住者も日本の医療保険でカバーされるため、実際に日本で生活していない人々の医療費も補助対象となり、不適切な負担増につながっている。
また、外国人労働者や留学生による医療費未払い問題はとても深刻だ。
2021年9月の調査では、外国人患者による未払い金は1億2000万円以上と報告されている。
【 就職市場に与える影響】就職活動の競争が加速する理由

日本で学ぶ中国人留学生の数が増加し続ける中、就職市場や教育機関に新たな課題が浮上。
競争激化、教育負担の増加、そして不法就労のリスクなど、多岐にわたる影響が出始めている。
【競争激化 】中国人留学生の〇割が日本で就職希望?
2025年3月、日本の大学を卒業した中国人留学生の約6割が日本での就職を希望。
東京都内の大手電機メーカーの人事担当者は「中国人留学生の応募が急増し、日本人学生との競争が激しくなっている」と語る。
特に、IT関連や研究開発職での競争が顕著だという。
【 教育機関の負担増加】中国人留学生の急増に対応するには?
中国人留学生の増加は、大学や大学院の教育現場にも影響を与えている。
特に理系の研究室では、留学生の割合が高くなり、教員の負担が増加しているという。
京都の国立大学で教鞭を執る山田教授(仮名)は「研究指導や論文指導で言語の壁に直面することが多く、時間がかかる」と指摘する。
また「日本人学生への指導時間が相対的に減少している」と懸念を示した。
【不法就労の問題】約〇万人の中国人が不法残留者!?
留学生の増加に伴い、不法就労のリスクも高まっている。
法務省の統計によると、2024年の不法残留者のうち、中国人は約1万人で2番目に多い。
「不法就労」とは、日本で就労する資格を持っていない外国人が日本で働くことを指す。
大阪のコンビニエンスストア経営者は「留学生アルバイトの中に、週28時間の制限を超えて働く者がいた」と明かす。
こうした事例は、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性がある。
これらの課題に対応するため、大学や企業では留学生向けの就労ルール説明会の開催や、多言語による指導体制の整備など、様々な取り組みが始まっている。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
日本の大学における中国人留学生の急増は、少子化対策や大学の安定化という日本側の事情と、優遇措置や教育環境を求める中国側の需要が合致した結果だといえるだろう。
しかし、医療費高騰や就職競争の激化、教育現場での課題など、様々な影響も生じている。
政府の「留学生40万人計画」を進める中で、公平性の確保と社会統合のバランスをどう取るかが今後の大きな課題となるだろう。
この記事が留学生問題への理解を深める一助となれば幸いだ。

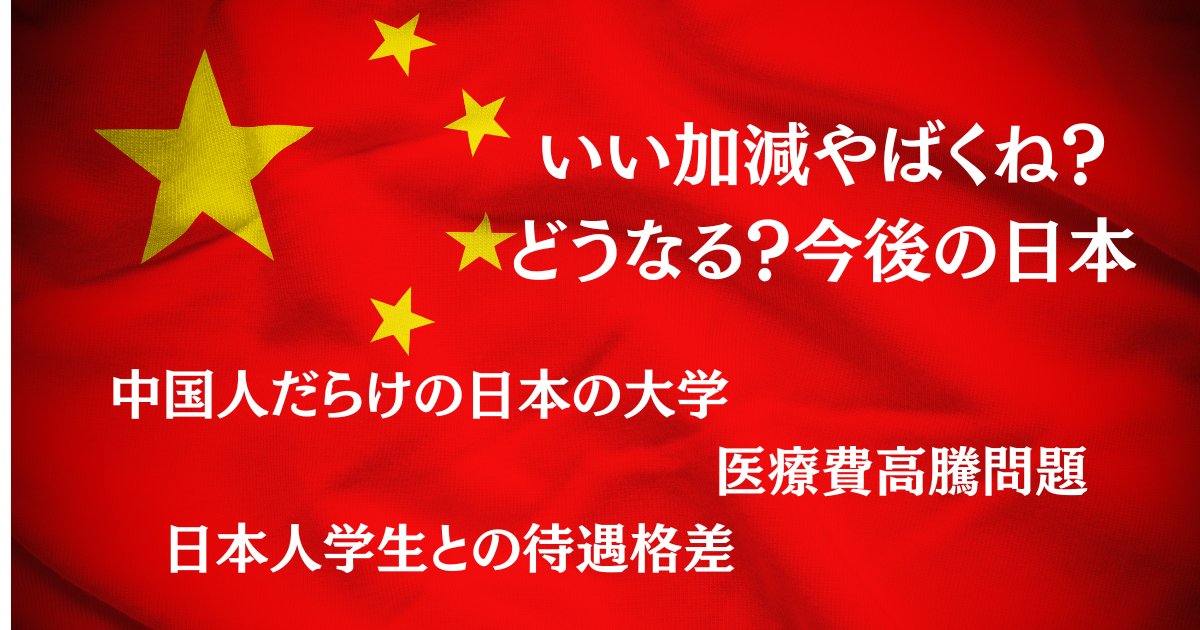

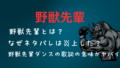
コメント