三重県の吉田紋華県議(27)が公共施設のトイレに生理用品が設置されていなかったことで困った経験をXで発信し、ナプキンの設置を訴えた。
「トイレットペーパーみたいに、生理用ナプキンをどこでも置いてほしい」
という投稿には批判的な意見も寄せられたが、女性の約5人に1人が生理不順を経験する現実もある。
本記事では、「急な生理への対応策」「公共施設でのナプキン設置の課題」「無料配布と有料販売のメリット・デメリット」「そして生理不順の実態」まで、この問題を多角的に掘り下げていく。
「公共トイレにナプキン設置を」吉田紋華三重県議のXへの投稿が話題に

突然の生理に慌てた経験は多くの女性に当てはまるだろう。
25日、全国最年少で当選した共産党の吉田紋華三重県議(27)のXでの投稿が話題となった。
吉田県議は、
「今日いきなり生理になって困った」と投稿した。
続けて「用があって寄った津市役所のトイレにはナプキンは残念ながら配置されてなかった」と明かし、「家に帰るまでちゃんと対処できなかった」「27歳でもこんなこと起こります」と説明。
自身の経験から「トイレットペーパーみたいに、生理用ナプキンをどこでも置いてほしい」と訴えた。
この投稿に対しては、
「役所内にコンビニあるのに行かなかったんだ」
「学生じゃあるまいしハンカチとおんなじくらいナプキン持ち歩かない?」
「置くならナプキンの自販機。そうでないと持ち帰られてあっというまになくなる」
などの冷たい意見が多く寄せられた。
急な生理でナプキンがない!身近なもので即効対処する4つの方法

突然の生理でナプキンがない場合、身近なもので対応することが可能だ。
以下に具体的な代用品と使い方を紹介する。
1. トイレットペーパーを使った応急処置
まず最も手に入りやすいのがトイレットペーパーだ。
使用方法は簡単で、1〜2cmの厚さになるようにトイレットペーパーを巻き、下着に置く。
長さや幅は通常のナプキンと同じくらいにするとよい。
ただし水に弱くすぐ破れる可能性があるため、こまめな交換が必要になる。
2. ティッシュペーパーの活用法
ティッシュペーパーも代用品として使える。
吸水性があり肌触りも柔らかいため、短時間なら十分に機能する。
ただし経血量が多い場合は長時間の使用は避けたほうがよい。
3. キッチンペーパーの使い方
水分に強く吸水性に優れているキッチンペーパーは、代用品として特に適している。
トイレットペーパーよりも破れにくく、より長い時間使用できる。
4. ハンカチやミニタオルの併用テクニック
清潔なハンカチやミニタオルをトイレットペーパーと組み合わせると効果的だ。
トイレットペーパーを内側に、ハンカチを外側に配置することで、吸水性と漏れ防止の両方に対応できる。
ただし、こうした応急処置は決して快適なものではない。
下着に異物を挟む不快感や、漏れる不安を抱えながら過ごすストレスは計り知れない。
多くの女性は「何も変えずにそのまま使用する」選択を迫られ、心身ともに負担を強いられている現実がある。
【生理トラブルを未然に防ぐ】長期的な対策と準備

応急処置だけでなく、長期的な視点での対策も重要だ。
生理予測アプリを活用して周期を把握しておくことで、次回の生理に備えることができる。
また、生理用品を常に持ち歩く習慣をつけることも大切だ。
小さなポーチに数枚入れておくだけで安心感が違う。
さらに、布ナプキンや吸水ショーツなど再利用可能な選択肢も増えている。
これらは長時間使用可能で、環境にも優しい選択肢として注目されている。
しかし、外出先で急に生理が来た場合には、これらの代替品が手元にないことがほとんどだ。
そのため、公共施設へのナプキン設置の重要性は依然として高いままと言えるだろう。
「ナプキン持参は常識?」5人に1人が生理不順・不規則な女性の体

吉田県議の投稿に対しては、
「学生じゃあるまいしハンカチとおんなじくらいナプキン持ち歩かない?」
「役所内にコンビニあるのに行かなかったんだ」
といった批判的なコメントも多く寄せられた。
こうした意見は一見すると理にかなっているように思える。
大人の女性なら生理用品を常に持ち歩くべきという考え方だ。
しかし、女性の体の不規則性を考慮した意見かと言われれば疑問が残る。
厚生労働省の調査結果によれば、約5人に1人(21.8%)が生理不順を経験している。
また、生理周期が24日より短い女性が12.4%、39日より長い女性が14.1%と、合わせて26.5%の女性が正常範囲外の周期で生理を迎えている。
特に10代女性では約30%が月経不順や無月経を報告しており、若年層でより一般的な悩みとなっている。
つまり、生理の予測が難しい女性は少なくなく、「持ち歩くのが当然」という意見には一理あるものの、女性の体の多様性や不規則性を考慮していない部分がある。
理想論としては正しくても、現実の女性の体験に寄り添っているとは言えないだろう。
吉田県議も「27歳でもこんなこと起こります」と訴えているように、年齢に関係なく予期せぬ生理に直面することは珍しくないのだ。
公共施設のトイレにナプキン設置は実現可能?無料vs有料の徹底比較

吉田県議の「トイレットペーパーみたいに、生理用ナプキンをどこでも置いてほしい」という訴えに対し、市当局は消極的な姿勢を示したという。
公共施設でのナプキン設置には、コスト負担や乱用リスク、管理の問題など様々な課題がある。
そこで、無料配布と有料販売という二つの方法に焦点を当て、それぞれのメリットとデメリットを詳しく見てみよう。
生理の貧困解消!無料配布が実現するメリット
無料配布は多くの利点を持つ。
まず、経済的負担の軽減が挙げられる。
特に経済的に困難な状況にある人々にとって大きな助けとなる。
生理用品にかかる費用を節約でき、他の必要な支出に回せるようになる。
また、突然の生理開始や予期せぬ状況に即座に対応できる点も重要だ。
現金や電子マネーを持っていなくても、すぐに使える安心感がある。
これにより、女性の社会生活や学業に支障が出ることを防ぐことができる。
さらに、経済的理由で生理用品を購入できない状況(生理の貧困)を直接的に解決する手段となる。
これは単なる経済的支援だけでなく、女性の尊厳を守ることにもつながる。
【予算と管理の】無料配布の現実的課題
一方で、無料配布にはいくつかの課題も存在する。
最大の問題は施設側のコスト負担だ。
無料配布を継続的に実施するには相当の予算が必要となる。
特に小規模自治体では財政的に厳しい場合が多い。
また、乱用や持ち去りのリスクも無視できない。
誰でも自由に使える状況では、必要以上に持ち去られたり、目的外使用されたりする可能性がある。
これは資源の無駄遣いにつながる。
さらに、在庫管理の必要性も大きな課題だ。
定期的な在庫確認と補充が必要となり、管理コストが発生する。
需要予測の難しさから、過剰在庫や品切れの問題も生じやすい。
【持続可能な提供へ】有料ナプキン設置のメリット
有料販売の最大のメリットは、持続可能な提供体制を構築できる点だ。
利用者からの支払いにより、継続的かつ安定した提供が可能となる。
予算に左右されにくく、長期的な支援体制を維持しやすい。
また、有料であることで、必要以上の使用や持ち去りを抑制する効果がある。
これにより、真に必要な人々に確実に提供できる可能性が高まる。
さらに、品質管理がしやすいという利点もある。
有料販売の場合、品質に対する要求が高まるため、より良質な製品を提供する動機付けとなる。
利用者の多様なニーズに応じて、複数の製品の選択肢を提供することも可能だ。
緊急時に使えない?有料ナプキン設置の落とし穴
有料販売の最大の課題は、経済的負担が残ることだ。
生理の貧困対策としては不十分な可能性がある。
特に経済的に困難な状況にある人々にとっては、少額であっても負担となる場合がある。
また、現金や電子マネーを持ち合わせていない場合、緊急時に対応できないという問題も生じる。
特に若年層や観光客など、準備していない人々は困る可能性が高い。
さらに、販売機の設置には場所やコストの制約があるため、必要な場所すべてに設置することが難しい。
トイレの個室すべてに設置するのは現実的ではなく、プライバシーの問題も生じる可能性がある。
「置くならナプキンの自販機。そうでないと持ち帰られてあっというまになくなるのが分からないんだろうか」
という意見もあるように、有料販売を支持する声もある一方で、緊急時の対応という点では課題が残る。
生理用品メーカーへの影響は?市場変化の可能性
公共施設での無償配布が進んだ場合、生理用品メーカーにはどのような影響があるのだろうか。
一般消費者向けの販売量が減少する可能性がある一方で、自治体や公共施設という大口顧客との取引機会が増加するだろう。
また、環境意識の高まりを受けて、環境に配慮した製品開発が促進される可能性もある。
さらに、多様なニーズに対応した製品ラインナップの拡充が進むことも考えられる。
データで見る女性の健康 ~生理不順の実態と対策~
生理不順は多くの女性が経験する健康課題だ。
厚生労働省の調査では、約40%の女性が生理の症状に対して「我慢」という対処行動を取っていることが明らかになった。
この高い割合は、適切な対処法や医療サポートの必要性を示唆している。
生理用品の公共施設での提供は、単に緊急時の対応だけでなく、女性の健康と社会参加を支える重要な取り組みと言える。
まとめ:生理用品の公共施設設置は「便利」以上の意味がある
吉田県議の訴えをきっかけに、生理用品の公共施設設置について様々な視点から考えてきた。
急な生理への対応策から、設置の難しさ、持ち歩きの現実、メーカーへの影響、そして女性の健康課題まで多角的に検討した。
生理用品の公共施設設置は、単なる「便利」以上の意味を持つ。
それは女性の社会参加を支え、経済的弱者を支援し、健康課題に向き合う社会の姿勢を示すものだ。
コスト負担や運用面での課題はあるものの、それらを乗り越える価値のある取り組みと言えるだろう。
吉田県議の「トイレットペーパーみたいに、生理用ナプキンをどこでも置いてほしい」という訴えは、多くの女性の声を代弁するものだ。
この問題に対する社会の理解と対応が進むことを期待したい。


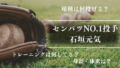

コメント